日本では台風や地震など毎年何かしら大きな災害が発生し、連日ニュースになったりしていますね。
特に近年は発生する災害の規模が大きいように感じます。
数年前に友人に結婚祝いのプレゼントを贈ったところ、お返しに防災グッズが送られてきました。
「最近災害が多いから気をつけよう。頑張って生き抜こう!」と言われました。
防災グッズを貰うとは・・・やはりそれだけ災害が多く起きていて、人々の防災意識も高まっているということだと思います。
人のことだけでなく、一緒に暮らす動物の避難についても日頃から対策を考えておきたいものです。
そこで今回は、日頃からやっておきたい犬猫の災害対策をまとめてみたいと思います。
飼い主情報がわかるものを動物に装着する
災害時には動物と離れてばなれになってしまうことがあります。
雷や地震などに驚いて家から脱走してしまう犬猫の話も珍しくありません。
動物が迷子になってしまった時に、何かしら飼い主情報がわかるものが体に付いていれば、見つけてくれた人が連絡をくれるかもしれません。
そもそも犬の場合は狂犬病予防法により、鑑札と狂犬病予防注射済票は災害の発生に関わらず装着することが義務となっています。
それ以外にも、首輪に飼い主情報の書かれた迷子札を付けておいたり、マイクロチップを挿入しておくなどの方法があります。
猫の場合は首輪に迷子札を付けるか、マイクロチップを挿入するかのどちらかの方法がほとんどだと思います。
災害時の話ではありませんが、迷子でウロウロしていた犬が通りすがりの人に保護され、動物病院へ来ることがあります。
首輪についていた情報をたよりに飼い主の元へ帰ることができた事例はよくあります。
純血種の猫が何日も外をウロウロしており、保護した人が動物病院へ連れてきてマイクロチップが入っていたことにより飼い主が判明したこともあります。
なので、災害時に限らず飼い主情報を明示しておくことはおすすめします。
ちなみにマイクロチップを挿入する場合は、飼い主情報の登録を忘れないようにしましょう。
マイクロチップ自体に飼い主情報が入っているわけではなく、マイクロチップには15桁の数字が記録されています。
その数字をデータバンクに問い合わせすることにより、飼い主情報が得られるという流れです。
つまり、マイクロチップ番号と飼い主情報を紐づける登録手続きを行っておかなければ、マイクロチップが挿入されていてもあまり意味がありません。
登録情報に変更がある場合も、早めに変更の手続きをしておきましょう。
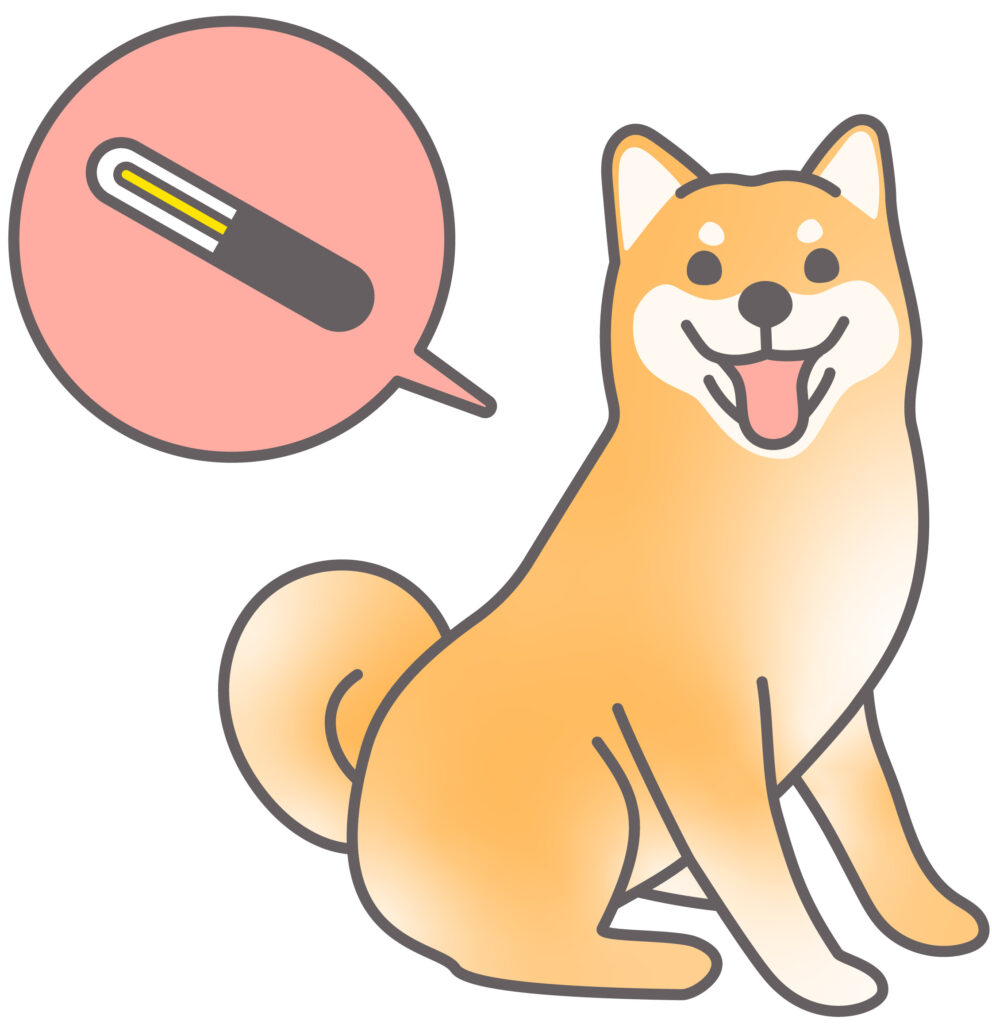
逆に、飼い主の方から迷子になった犬猫の居場所をすぐにつきとめたいという場合は、GPSを首輪などに付けておくという手もあります。
しつけをする
日頃から様々なしつけをしておくことは災害時に限らず何かと役に立つと思います。
ぜひチャレンジしてみてください。
非常時のためにも特に身につけておきたいことを以下にあげます。
キャリーに慣らす
災害時、一緒に避難する場合はキャリーに入ってもらう必要が出てくるかもしれません。
キャリーに慣れていない子にとっては、ストレスを感じる可能性があります。
日頃からキャリーの中に入ってくつろいだり、眠る習慣をつけておくと、速やかに避難行動ができ、避難生活においてもストレスが少なく過ごせるかもしれません。
日頃からキャリーに入れて近くへお出かけしてみるのもいいかもしれません。

おすすめのキャリーについて別記事でまとめていますので、もしよければ参考にどうぞ↓
様々な環境に慣らす
日頃からいつもと違う道を散歩したり、お出かけして様々な環境を体験させておくことで、災害時の環境にも動じなくなるかもしれません。
車内で避難生活をする可能性も考えて車に慣らしておくのもいいかもしれません。
車に居させる場合は車内での熱中症にも注意が必要です。
そのあたりも含めて一度訓練しておくと、いざという時にあたふたしなくて済みそうです。
どうしても性格的に環境の変化に弱い子もいると思うので、その場合は無理しない程度に訓練しておくといいと思います。
知らない人に触られることや、他の動物が近くにいても大丈夫なようにしておくこともおすすめです。
室内でのトイレトレーニング
犬の場合ですが、排便・排尿は散歩に行ったときなどに外でさせることが多いのではないでしょうか。
外でしかしない、家の中で排泄しない子は結構多いように思います。
中にはコンクリートやアスファルトではダメで、土の上じゃないと排泄しないという強いこだわりを持っている犬も目にします。
災害時はいつものように散歩に行けるかわかりませんし、どこかに預けることになった場合、その場所では室内で排泄しなければならないかもしれません。
慣れていない子は排泄を我慢してしまいます。
犬の場合、丸一日我慢してしまう子も珍しくないです。
24時間もトイレに行かせてもらえない状況を自分自身で想像してみてください。辛いですよね。
最終的には我慢できずに排泄するのですが、我慢している間は辛いはずです。
体にも良くありません。
こういった状況に陥ることも想定して、室内でペットシーツなどの上で排泄できるようにトレーニングしておくといいと思います。
その他、避難所で吠えてしまうと周囲に迷惑がかかる可能性があるので、無駄吠えしないようにしつけておくのもおすすめです。
基本的な”お座り”や”待て”を覚えておくと他のしつけをする際や何か問題行動をやめさせる際にも役に立つのですごくおすすめです。
動物用避難用品の準備
避難する際に持ち出す物を日頃から用意しておくと、いざという時にスムーズに動けるでしょう。
避難用品の例を以下に挙げてみます。
- フード、水、食器
- 薬
- ペットシーツ、糞尿処理用品、新聞紙、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、ビニール袋
- 首輪・胴輪、リード(余裕があれば予備も準備)
- キャリー、折り畳みケージ
- ワクチン証明書etc…
- 猫の場合はトイレ用猫砂、洗濯ネットなど
持病のある子の場合は、最近の健康状態がわかる血液検査の結果や服用中の薬の名前や用量・用法がわかるものがあると役に立つかもしれません。
日頃から健康管理手帳のようなものを作成しておくのもおすすめです。
動物病院などで貰える場合もありますので、かかりつけで聞いてみるといいかもしれません。
フードや薬は可能なら1週間分くらい、最低でも5日分くらいは持ち出せるといいと思います。
動物の一時預け先の確保
動物と一緒に同伴避難できなかった場合を想定し、あらかじめ非常時の預け先を考えておきましょう。
特に大型犬だったり、犬猫以外の特殊な動物は預け先が簡単に見つからないかもしれないので、日頃から探しておくことをおすすめします。
これは災害時に限ったことではなく、何か急に用事が出来て遠出しなければいけない時や旅行に行くのに動物を連れて行けない時にも役に立ちます。
預け先によっては、預かる条件としてワクチンの接種やノミ・マダニの駆除薬の投与などが必要な場合があるので、事前に条件や費用なども確認しておきましょう。
避難場所までの経路や所要時間の確認
実際に災害が起きたときにどこへ逃げるか、その場所までの経路や所要時間がどれくらいかも知っておきましょう。
避難所までの経路に回避した方がよさそうな危険な場所が無いかも要チェックです。
いざという時に通れないという予想外の事態が発生しないようにしましょう。
ペット同行避難訓練を実施している自治体も結構あるので、参加してみるといいかもしれません。
興味がある方はお住まいの自治体でも実施しているか調べてみてください。

今回は以上です!
災害は突然やってきますので、平常時から被災した際の備えをしておきたいものです。
参考になれば嬉しいです。
追加情報があれば随時更新します。
【PR】










コメント