近年私のまわりで少し話題になっている感染症があります。
レプトスピラ症という感染症なのですが、犬の混合ワクチンにも含まれていたりするので名前を聞いたことがある方も多いかもしれません。
「近くで何件か発生しているので注意してください」という連絡がまわって来ています。
レプトスピラ症はレプトスピラという細菌が原因となる病気で、人にも感染します。
犬の混合ワクチンで予防できる病気の中で、唯一人でも問題になる病気です。
そのため、感染の可能性がある犬を見かけたら診察時も注意しなければなりませんし、この病気が見られたら家畜保健衛生所に届出をしなければなりません。
動物から人にうつる病気は多々ありますが、その中でも届出が必要なレベル。それはつまり危険な病気ということです。
今日はレプトスピラ症について解説していきます。
レプトスピラ症の原因
レプトスピラという細菌が原因になります。
レプトスピラはスピロヘータ目レプトスピラ科に属し、らせんの形をしています。ちなみにグラム陰性菌です。
病原性のレプトスピラと非病原性のレプトスピラがあり、問題になるのはもちろん病原性レプトスピラです。
後ほど話が出てくる予定なのですが、一言でレプトスピラと言っても、レプトスピラにはかなり多くの血清型が存在します。
病原性のあるL.Interrogansでは250以上も血清型が確認されています。
なので血清型まで正確に書こうとすると、
Leptospira interrogans serovar Canicola
Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae
のように長ったらしくなります。
今はとりあえずレプトスピラと一言でくくらせてもらいます。
これらの病原菌は野生動物、中でもネズミなどの齧歯類が高率に保菌しています。

ネズミの尿中にレプトスピラが排泄され、水(池、川、水溜まり、水路、田んぼ、湿地など)や土壌を汚染します。
レプトスピラは水中で長期間生存することができます。
尿に汚染された水や土壌に接触することで皮膚や粘膜からレプトスピラが感染します。
ネズミを捕食することでも感染することがあります。
ちなみに宿主域は広く、ほとんどの哺乳類が宿主になります。
保菌期間は動物によって異なりますが、感染した犬は回復した後も数か月から数年に渡って尿中にレプトスピラを排菌するため、感染源となります。
レプトスピラ症の症状
以下のような症状があります。
発熱
下痢
嘔吐
黄疸
粘膜の充血
肝障害
腎障害
舌の壊死
貧血
ヘモグロビン尿
粘膜の出血
点状出血
紫斑
タール便
敗血症性ショック
DIC
血清型により症状は異なり、多くは感染しても症状がみられなかったり、軽症で済みます。
中でも犬で比較的発生が多く、症状が重症化しやすいという点で注目しておきたい型はL.canicola、L.Icterohaemorrhagiaeです。
このほか届出には指定されていませんがL.Hebdomadisによる症例も多く発生しています。
他、L.Castellonis、L.Pyorogenes、L.Poi、L.Copenhageniなど多数の型が報告されていますが、挙げていくと大変なのでこのへんにしておきます。
L.Canicolaは嘔吐、脱水、虚脱、口腔粘膜・舌の壊死、腎炎などの症状を特徴とし、L.Icterohaemorrhagiaeは肝障害、黄疸、皮下や粘膜の出血などの症状が特徴とされています。どちらも重度の場合は死亡します。
犬(牛、水牛、豚、鹿、イノシシも)で発生した場合、届出に指定されている血清型は以下の7種類です。
L.Icterohaemorrhagiae
L.Canicola
L.Pomona
L.Hardjo
L.Grippotyphosa
L.Autumnalis
L.Australis
レプトスピラ症の診断
問診、身体検査、血液検査、画像検査を組み合わせ、レプトスピラ症が疑わしい場合は血液や尿を検査機関に送り、調べます。
血清中の抗体価を測定したり、血液・尿からPCR法で遺伝子を検出することで確定診断を行います。

レプトスピラ症の治療と予後
レプトスピラ菌に対してはアンピシリンやドキシサイクリンなどの抗菌剤が有効です。
その他、輸液、血液抗凝固薬の投与など、症状に合わせて治療を行います。
治療が遅れると重症化し死亡する確率が上がるので早期の治療が大切です。
回復後も腎臓に障害が残ってしまうことがあります。
また、しばらくは尿中に菌が排泄されるため、他の動物や人に感染させないように管理する必要があります。
素手で尿に触ったりしないように注意してください。
同居の動物がいる場合は別の部屋で生活させましょう。
レプトスピラ症の予防
まずはネズミがいそうな場所にはなるべく立ち入らないようにすること。
とは言ってもネズミは都会でも生息しており、感染を引き起こしています。
気をつけるようにしていてもなかなかふだん普通に散歩にも行くでしょうし、避けきれないと思います。
次に、ワクチンがあります。
ただし、先ほどからお伝えしている通り、レプトスピラには多くの血清型が存在しています。
何を言いたいか、おわかりでしょうか。
ワクチンはレプトスピラであれば全ての血清型を防いでくれる訳ではなく、残念ながら特定の血清型に対してしかワクチンが開発されていません。
まず、国内で販売されている混合ワクチンでレプトスピラの効果が含まれているのは、7種混合ワクチン、8種混合ワクチン、10種混合ワクチンです(2025年5月現在)。
以前は9種混合ワクチンもありましたが販売が終了してしまいました。
他にレプトスピラ単体のワクチンが販売されており、2種もしくは4種の血清型に対して有効です。
以上のワクチン全てにL.Canicola、L.Icterohaemorrhagiaeに対する効果は含まれています。
10種混合ワクチンや4つ入ったレプトスピラワクチンでL.Pomona、L.Grippotyphosaの予防も可能です。
逆に言うとこれらの限られたレプトスピラに対してのワクチンしかなく、ワクチンを接種していても、感染した血清型が違ってしまえば発症する可能性があるということです。
また、レプトスピラのワクチンはコアワクチンに比べて効果が長続きしないため、毎年の追加接種が必要です。
他のワクチン(5種や6種ワクチン)に比べ、レプトスピラが含まれているワクチンは副作用が出る頻度も少し高い印象があります。
このようなデメリットもありますが、ネズミが居そうな場所によく出かける、水遊びによく行く、山にキャンプに行く、他の犬との接触が多い、近所でレプトスピラの発生があったなど、感染のリスクがありそうな場合はワクチンの接種をおすすめします。
発生は夏から秋に多いため、ワクチンを接種するなら夏より前に接種しておくのがおすすめです。

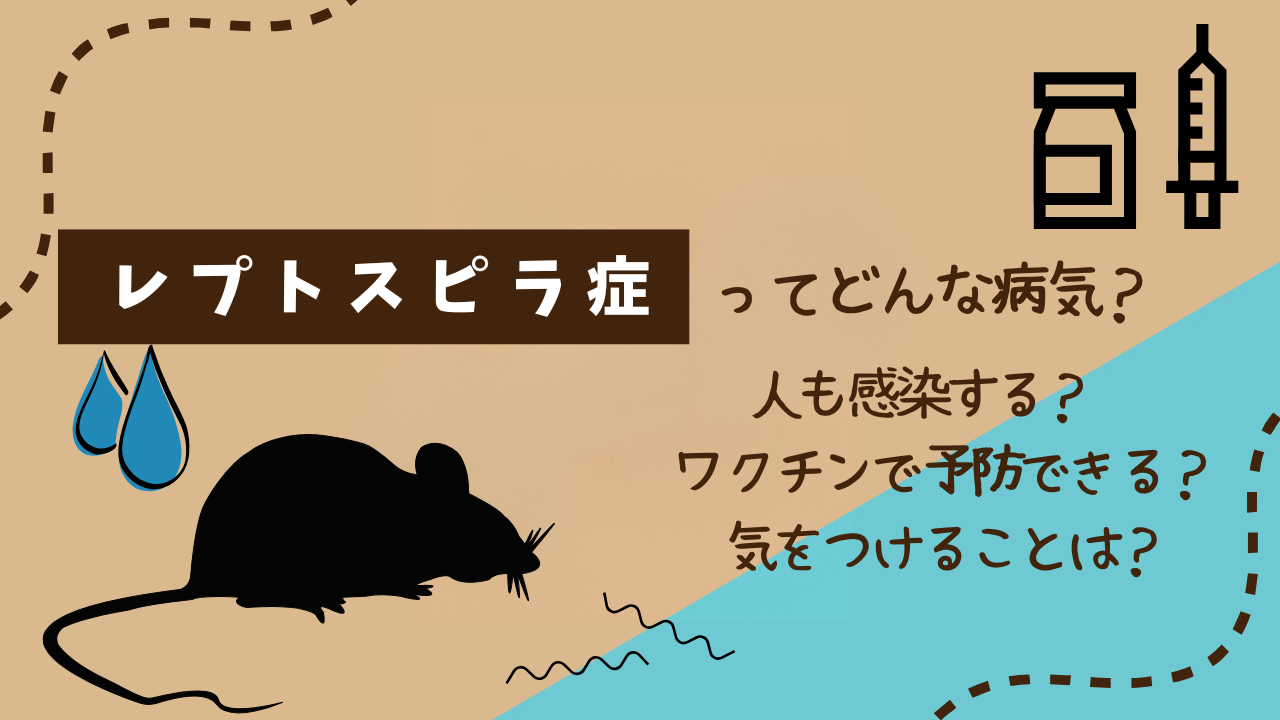

コメント