今日は野良猫を拾った時のお話をしてみようと思います。
道端で子猫を拾ったと病院へやって来る方が毎年何人かいらっしゃいます。
子猫が生まれる時期は特に連れてくる方が増えます。
庭にやってくる大人の野良猫が懐いてきたから家に入れたいけれど、その際に何をしておいた方がいいの?という質問を受けることもあります。
何年も前から近所をウロウロしていて、色んな人からご飯を貰っているようだが、年を取ってきて外の環境では辛そうだから家に入れてあげたいと相談される場合もあります。
今回は野良猫を家に入れる際におすすめしたい処置や検査についてお話します。
野良猫といっても、子猫の場合もあれば成猫や高齢猫の場合もあると思いますし、
健康そうな猫の場合もあれば体調が悪そうな場合もあるでしょう。
拾ったらまずは動物病院へ連れて行って、怪我していないか、健康状態はどうか、診察を受けるといいと思います。
その際に今後何をするべきか獣医師と相談してみてください。
いくつかおすすめを以下に書いておきます。
①ノミ駆除薬の投与
まずはじめに欠かしたくないのはノミの駆除です。
ほとんどの場合、拾った直後はノミがついています。
猫を飼うのが初めてという方はノミがどんな姿をしているかわからないかもしれません。
猫の皮膚表面をとても小さい黒~茶色いものが素早く走っていたら、かなりの確率でそれはノミです。
黒ゴマよりも小さいです。でも肉眼で十分確認できる大きさをしています。
動きが素早いので、すぐに見失ってしまうかもしれません。
慣れている場合、指で捕まえることもできます。
猫の体から離れると、ものすごい跳躍力でジャンプします。
そうなるとどこへ行ったかわからなくなります。
猫を家に持ち帰ってそのまま家の中で放してしまうと、ノミが家の中に入ってしまい、人もノミに咬まれて痒い思いをしたり、家の掃除が大変になります。
最初は猫を隔離して、ノミ駆除をしましょう。
ノミ駆除薬は動物病院で処方してもらうといいと思います。
年齢や体重によって使用できる薬が変わってきますので、猫を連れて動物病院を訪れましょう。
猫の体が汚れている場合は洗ってあげてもいいと思いますが、洗うだけでは汚れは取れてもノミはなかなか取れないので、ノミ駆除薬の使用をおすすめします。
稀にノミがあまり寄生していなさそうな野良猫も見かけます。
でも見ただけで絶対ノミがいないとは断言できないので、ノミの姿が確認できなくてもノミ駆除薬は投与しておいた方がいいでしょう。
ノミの成虫が確認できなくても、ノミの糞があればノミがいる可能性は高いので、ノミ糞を探してみてもいいと思います。
ノミ糞は黒い砂のような見た目をしており、時々細長いものもあります。
ノミ糞らしき砂粒を見つけたら、濡らしたティッシュなどにこすり付けてみてください。
ティッシュに赤っぽい色が染み出てきた場合、それはノミ糞の可能性が高いです。
ノミは吸血する寄生虫ですので、ノミ糞には血液成分が含まれています。
そのため、濡らすと血液成分の赤色が染み出てくるという訳です。
そうやってノミ糞なのかただの砂なのか鑑別してみるといいと思います。
ノミ糞が多く見られやすい場所は、猫の背中のしっぽの付け根付近です。
そこの毛をかき分けて、黒い粒が無いか探してみてください。
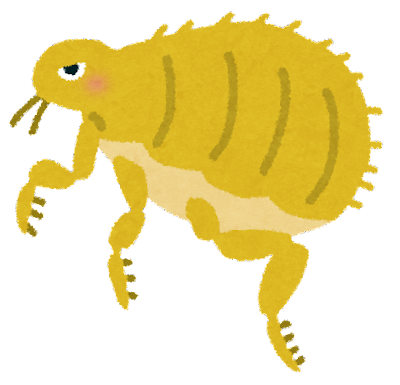
②猫エイズ・白血病検査(FIV/FeLV検査)
猫エイズとは、猫免疫不全ウイルス感染症のことです。
白血病は猫白血病ウイルス感染症です。
野良猫はこれらのウイルスに感染していることがあり、すでに感染している場合は体内からウイルスを排除することはできません。
ウイルスを持っているからと言ってすぐに死んでしまうということではないのですが、ウイルスを持っている場合はなるべくストレスを与えないようにするなど注意が必要になります。
これらの病気に感染しているかどうか、絶対に確認しておいた方がいいのは、すでに家に先住猫が居る場合です。
同居させるにあたり、同居猫に感染する可能性があるからです。
これらのウイルスは唾液を介して感染します。
エイズウイルスの方はケンカするなどして咬みついた時に唾液中のウイルスが傷口から感染します。
白血病ウイルスは同じお皿を使ってご飯を食べたりして感染してしまうことがあります。
そのため、ウイルスを持っているかどうかで、同居猫と同じ空間で生活させるか、隔離するべきか判断が別れます。
一度感染すると一生持ち続けることになるウイルスです。
感染させないことが大切です。
今は家に猫が居なくても、例えば今後友人の猫が家に遊びに来る機会があるかもしれません。
逆にどうしても誰かに猫を預かってもらわなければいけない状況に陥ることがあるかもしれません。
預け先には猫がいる可能性もあります。
そんな時に、ウイルスを持っているかどうかで、猫同士を接触させて大丈夫かどうかがわかります。
なので検査をしてウイルス陽性か陰性か知っておいた方がいいです。
ちなみに人には感染しません。
これらの病気についても今後お話したいと考えていて、いつか記事を書きます。
感染初期に検査しても陽性と出ない可能性があるので、検査の実施時期には注意です。
詳しくは動物病院で獣医師に聞いてみてください。
③糞便検査
お腹の中に寄生虫がいることも珍しくありません。
よく遭遇する寄生虫には回虫、条虫、コクシジウムなどがあります。
便に虫が出てきて飼い主さんが気づくこともあれば、やたら下痢・軟便が続いて検査してみて発見することもあります。
たまたま健康診断の一環で糞便検査を実施して寄生虫を見つけることも稀にあります。
良い形の便が毎日排泄されているのであれば、問題ないことが多いかもしれませんが、それでも時々寄生虫がいることがあります。
軟便や下痢が出た場合は、全てが寄生虫のせいでは無いですが、野良猫の場合はまぁまぁな割合で寄生虫が見つかる印象です。
怪しい場合は新鮮な便を動物病院へ持って行ってみてください。
一回の検査で確実に寄生虫が検出されるとは限らないので、特に下痢が続くという場合は何度か糞便検査をするのがおすすめです。
ちなみに新鮮な下痢便の中にしか姿を現わさない寄生虫もいます。
時間が経つと形を変えてしまい、そうなると特殊な染色をしなければ発見できなくなります。
糞便検査では虫体そのものを検出する場合と、虫卵を検出する場合があります。
寄生してから便に虫卵が出てくるまでには少し時間がかかり、その日数は寄生虫の種類によって異なります。
つまり、寄生虫に感染している野良猫を拾ったとして、感染してからの日が浅いと、すぐに糞便検査をしても何も見つからないということになります。
母猫が寄生虫に感染しており、乳汁を介して子猫に感染していたりすると、比較的早めに子猫の便から虫卵が見つかるかもしれません。
猫回虫はこのパターンがよくあります。
瓜実条虫という寄生虫は猫が体に付いたノミを食べることで感染するので、ノミの駆除は内部寄生虫対策にもなります。
便の表面や寝床に小さな米粒みたいなものが付着していたら瓜実条虫かもしれません。
瓜実条虫が見つかった場合は同時にノミ駆除もお忘れなく。

糞便検査で見つかった回虫卵↑
④混合ワクチン接種
猫を拾ったら、まずはお家の環境に慣れるまで約1週間くらいは静かに過ごすことをおすすめします。
食欲や元気があるか、下痢してないかなどの様子を見た後で、体調が良さそうならワクチン接種をおすすめします。
1回目のワクチンは生後2か月頃を目安に接種するといいと思います。
早過ぎると、元々母親から授かった免疫力があるので、その免疫力がワクチンの効果を弱めてしまいます。
拾った猫だと生後何日くらいかわからないかもしれません。
動物病院で診てもらってください。
ちなみに、生まれた直後の子猫の体重は100gほどです。
栄養状態が良ければ、生後1か月で500gほどに成長します。
生後2ヵ月で900g~1kgくらいに成長する子が多いです。
栄養状態によって結構差がでます。雄と雌でも少し差がつきます。
全く情報が無い場合、私はこのような体重や栄養状態などからいつ頃が生後2か月か推測しています。
例えば500gの栄養状態が良さそうな子猫が拾われて来た場合、生後1か月くらいは経っていそうだと考えて、あと1か月経ったらワクチン接種に来てくださいとお話します。
猫ワクチンについては別で記事を書いているのでここでは詳細は省きますが、ワクチンで予防できるものには以下のような病気があります。
・猫伝染性鼻気管炎
・猫カリシウイルス感染症
・猫汎白血球減少症
・猫クラミジア感染症
・猫白血病ウイルス感染症
・猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)※混合ワクチンには含まれていないので単体で接種する
基本的には完全室内飼いであれば3種混合ワクチン(猫伝染性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症)でいいと思います。
外に出ていくような環境で飼育する場合は白血病が入ったワクチンがいいかもしれません。
また、現在は混合ワクチンでは予防できませんが、猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)も単体ではワクチンがあるのでうっておくといいかもしれません。
ワクチンは初年度だけ抗体価を十分上げるために1か月間隔を空けて2回接種することをおすすめします。
2年目からは1年に1回で十分だと思います。
よく見る病気としては、猫伝染性鼻気管炎や猫カリシウイルス感染症で、これらは猫風邪と言ったりします。
完全室内飼いで他の猫との接触が一切無くても、猫風邪を引くことはあるので、ワクチン接種はおすすめします。
ワクチンをうつと風邪をひかないか?といわれると、そういう訳ではありません。
ワクチンをうっていても猫風邪にかかります。
人の新型コロナウイルスと同じで、ワクチンをうっていても感染はしますが、重症化は防止できます。
猫の混合ワクチンで予防できる病気についてはこちらをご参照ください↓

⑤血液生化学検査
拾った猫がすでに年を取っていそうな場合は、どこか内臓が悪くないか調べておくのがいいかもしれません。
特に猫は腎不全になる子が多いです。
腎臓は悪くしてしまうと元に戻らないので、早期発見が大切です。
早めに見つけてケアしていくことで腎臓病の進行を遅らせ、長生きできるかもしれません。
エイズ・白血病の検査をするのであれば、どちらにしても採血が必要です。
採血量は少し多くなりますが、せっかく採血するなら同時に腎臓など血液生化学検査もやっておいても良いかもしれません。

以上が猫を拾った際のおすすめの検査・処置でした。
他に欲を言えば、ついでに耳の診察もしてもらうと良いかもしれません。
拾った猫の中には耳にダニが寄生している子も時々います。
先住猫がいる場合はその子にミミダニがうつってしまうかもしれませんので、注意です。
ノミ駆除薬として使用する薬で同時にミミダニも駆除できるかもしれませんが、ミミダニは効果の対象外という薬もあります。
ミミダニが寄生している場合は、真っ黒の汚れが耳介内側にべったり付き、拭いても翌日にはまた真っ黒になります。
痒みがあるのも特徴の一つです。
耳の中が真っ黒だからと言って、全てがミミダニのせいというわけでもなく、マラセチアというカビが感染していることもあります。
耳のトラブルを抱えている子も結構多く見るので、一緒に診てもらうといいと思います。
去勢・避妊手術を希望する場合は、月齢にもよりますが、家の環境に慣れて体調に問題が無いことを確認してからでいいと思います。
その際に麻酔下でマイクロチップも装着しておくといいかもしれません。
生後何カ月経てば手術できるかは動物病院によって多少差があるので、お近くの動物病院で尋ねてみてください。
最後に、動物病院へ行くときは、猫を洗濯ネットに入れて行くことをおすすめします。
特に大人の野良猫では初めての環境に驚いてパニックを起こしてしまうことがあります。
動物病院の中で逃げ回ってしまい、捕まえるのに一苦労ということも…。
結構必死で逃げ回るので、物を倒したり落としたり、診察室の物がめちゃくちゃになることもあります。
想像がつかないかもしれませんが、パニックに陥った猫はなかなかです…。制御できません。
人間が怪我してしまうことも普通にあります。
飼い主さんが頑張って抑えようとしてくれて猫に咬まれたり、引っ掻かれたりして怪我することもあります。
流血事件になることも珍しくなく、人間が病院へ行かなければならなくなります。
洗濯ネットに入っているだけで、これらの大惨事が大幅に防げます。
それと、野良猫を段ボールに入れて動物病院へ連れていくことはあまりお勧めしません。
生後間もない子猫のように機敏な動きができない猫なら特に問題は無いのですが、動きが素早い猫を段ボールに入れてしまうと、段ボールを開けた時に飛び出して逃げてしまうことがあります。
段ボールに入れるなら、先に洗濯ネットに入れてあると逃走が防止できてとても助かります。
しかし相手は野良猫です。
ある程度成長していて動きが機敏だと、洗濯ネットに入れるなんて無理! という場合もあると思います。
その場合はなるべく小さめのキャリーか箱に入れられると、蓋を開けるときに逃げ道を塞ぎやすく、逃走を防止しやすいです。
今回はここまでにします。
少しでもお役に立つ情報があるといいのですが。
今後も関連する情報を少しずつ書いていきたいと思います。
【PR】
動物病院に連れて行くときにはこのようなネットに入れると、万が一猫がパニックになって逃げようと暴れたときも安心です。↓
拾ったばかりの時は多くの場合体が汚れています。
家に入れるのに汚れていると気になる方が多いと思います。そんな時は、猫の体調にもよりますが、シャンプーしてきれいにしたいものです。
人用のシャンプーを使うのではなく、ペット用の物を使用しましょう。









コメント