毎日暑いですね。
熱中症にならないようにしっかり水分を摂取していますか?
この時期は冷蔵庫から冷たい飲み物がすぐに消えていきます。
私は浄水ポットで水道水を浄水し、水出し緑茶や水出しジャスミン茶を作っているのですが、作っても作ってもすぐに無くなっていきます。
めちゃめちゃ回転が早い。
以前は水道水を沸かしてお茶を作っていましたが、夏の暑い時期に台所で火を使うのは余計暑いし、冷ますのに時間がかかるので面倒に感じていました。
その後は2Lのペットボトルを買っていたこともありましたが、あっという間に2L飲み切ってしまうので、お金もかかるし、家に運ぶのも重いしで困っていました。
そこで数年前に浄水ポットを使い始めました。
カートリッジ代はかかりますが、それでもペットボトルを買うよりも安いです。
寝る前や出勤前に水とティーバッグをボトルに入れて冷蔵庫に入れておくだけで、仕事から帰ってきて冷たいお茶が冷蔵庫に出来上がっています。すごくおすすめ。
で、前置きが長くなりましたが、家にいる犬猫が毎日どのくらい水を飲んでいるか把握していますか?
「飲水量が多い」という主訴で動物病院へ来る子は結構います。
主訴ではなかったとしても、問診を進めていく中で「飲水量は多い」と証言する飼い主さんは結構多いです。
飲水量が多い場合は血液検査を行って腎臓が悪くなっていないか、血糖値は高くないかなどを検査したりします。
その検査で病気が見つかることも珍しくないです。
具体的な飲水量は把握していなくても、以前と比べて明らかに増えていると感じて診察に来る方が多いので、そこには何らかの異常があったりします。
どれくらいの量の水を飲んでいるかを把握している方はそう多くはなく、たくさん飲んでいるように見えて実際に測ってみると正常範囲内であることもあります。
飲水量が増える病気はたくさんあるので、ふだんからどれくらい水を飲んでいるか把握しておくことで、病気の早期発見に繋がることがあります。
ということで、本日のテーマは「飲水量」です。
お家で飲水量を測定し、病気の早期発見に繋げていただければ幸いです。
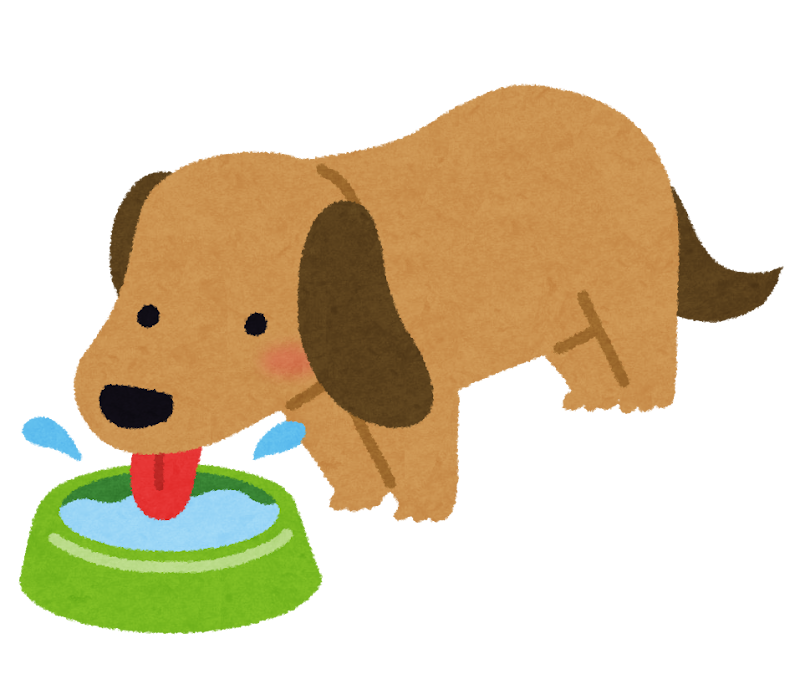
多飲と言われる飲水量の目安は?
そもそもどれくらい飲んでいたら異常なの?
まずは飲水量の異常値から紹介します。
多飲と言われる一日の飲水量の目安は以下の通りです。
犬…90ml/kg以上
猫…45ml/kg以上
上記の飲水量を超えて飲んでいる場合は何か病気が原因かもしれません。
多飲を引き起こす疾患は?
その原因疾患として、犬では糖尿病、腎不全、副腎皮質機能亢進症が多く、猫では腎不全、甲状腺機能亢進症、糖尿病が多いと感じます。
その他にも子宮蓄膿症、高ナトリウム食、薬の副作用(ステロイドや利尿剤など)、肝不全、尿崩症、心因性、発熱などなど。
多飲には様々な原因が考えられます。
特に猫において頻繁に遭遇する腎不全に関して言うと、早期発見がすごく大事な病気です。
腎臓はある程度悪くなってからでないと症状が出ず、気づいて病院に連れてこられた時には末期状態であることも珍しくありません。
初期症状に多飲多尿がありますが、よく観察していないとなかなか気が付かないこともあります。
腎臓は基本的には悪くなってしまうと元に戻らないため、腎不全は進行させないことが大切になってきます。
そのためにも早期に発見しておきたい病気です。
早期発見により、腎不全診断後も何年という単位で長く生きてくれる子もいます。
腎不全は多くの猫が罹患する病気ですので、いずれ記事を書きたいと思っています。
飲水量測定時の注意点
お皿に入れた水の量を測る場合は蒸発していく分もあるので注意です。
蒸発量はお水を置く環境によっても異なると思うので、一日でどのくらいの水がお皿から蒸発しているかも測ってみると良いかもしれないですね。
同じ量の水を入れた器を2つ置き、一つは動物が飲む用、もう一つは蒸発量測定用とすると手っ取り早く測定できるかもしれません。
蒸発量測定用のお皿からは水が飲めないようにバリケードでも作っておきましょう。
往診でちょこちょこお家にお邪魔するのですが、最近はメモリの付いたお皿を使用している方が結構多いように感じます。
これよく見かけます↓
【PR】
日頃からどれくらい水を飲んでいるのか観察し、早めに異常に気づけたら素晴らしいです。
ということで、お家でできる健康チェック2つ目のおすすめは「飲水量の測定」でした~。
飲水量とセットで尿量にも注目することをおすすめしますが、尿に関してはまた別の機会に書きたいと思います。
前回のお話、「やってみよう!お家でできる犬猫の健康チェック①~体重測定~」もぜひ参考にしてみてください。




コメント